下部消化管(大腸)内視鏡検査(大腸ファイバースコープ検査)画像診断
- 胸部X線検査(単純撮影)
- 上部消化管(食道・胃・十二指腸)X線検査
- 下部消化管(大腸)X線検査
- CT(コンピュータ断層撮影)検査
- MRI(磁気共鳴画像)検査
- MRA検査(磁気共鳴血管撮影)
- 気管支内視鏡検査
- 上部消化管(食道・胃・十二指腸)内視鏡検査(胃カメラ)
- 下部消化管(大腸)内視鏡検査(大腸ファイバースコープ検査)
- 心臓超音波検査(心エコー)
- 腹部超音波検査(腹部エコー)
- 頸動脈超音波検査(頸部血管エコー)
- PET(ペット)検査
- SPECT(スペクト)検査
どんなときに受ける?
大腸がんが心配なとき、大腸がんの疑いがあるときに受けます。
どんな検査?
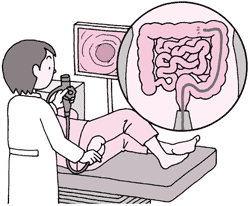
[下部消化管(大腸)内視鏡検査]
下剤を服用して腸をきれいにした後に内視鏡を肛門から挿入して、大腸(結腸、直腸)の中を直接観察して病変がないかを調べる検査です。病変がある場合は、病変の大きさや形状だけでなく、表面の色や出血のようすなども詳しく調べられます。またポリープなどの病変がみつけたときはそのまま切除したり、その場で組織を採取し、詳しい検査にまわせるメリットがあります。
検査時に大腸の中に便が残っていると検査の妨げになるため、検査のときは下剤で大腸をからにします。検査自体にかかる時間は、通常10~15分程度です。
検査で何が分かる?
大腸の内壁ほとんどを観察することができます。粘膜に生じたポリープやがん、炎症、潰瘍(かいよう)、憩室(けいしつ)などがわかります。憩室とは腸壁の一部がふくろ状に突出して小さなポケットができている状態です。
検査のときの注意/受けるときのポイント
内視鏡を入れるときは、口で呼吸をしておなかに力を入れないようにするとよいでしょう。
なお、検査前には、朝から2ℓの下剤を、3~4時間かけてのみ、腸の中をからにさせます。検査そのものより、これを苦痛に感じる人が多いようです。
痔をもっている人はこの検査を行えないことがあります。
異常があるときに疑われる病気
大腸がん(直腸がん、結腸がん)、大腸ポリープ、潰瘍性(かいようせい)大腸炎、クローン病など。
異常がみつかったら?
ポリープは高い確率でがんになる可能性があるため、5ミリ以上のポリープは、みつけたら切除するのが原則です。
がんの疑いがある病変がみつかった場合は、その場で組織を採取して、良性か悪性かを調べる病理検査を行います。
