CT(コンピュータ断層撮影)検査画像診断
- 胸部X線検査(単純撮影)
- 上部消化管(食道・胃・十二指腸)X線検査
- 下部消化管(大腸)X線検査
- CT(コンピュータ断層撮影)検査
- MRI(磁気共鳴画像)検査
- MRA検査(磁気共鳴血管撮影)
- 気管支内視鏡検査
- 上部消化管(食道・胃・十二指腸)内視鏡検査(胃カメラ)
- 下部消化管(大腸)内視鏡検査(大腸ファイバースコープ検査)
- 心臓超音波検査(心エコー)
- 腹部超音波検査(腹部エコー)
- 頸動脈超音波検査(頸部血管エコー)
- PET(ペット)検査
- SPECT(スペクト)検査
どんなときに受ける?
異常が疑われた場合の精密検査として受けます。人間ドックでは、肺がんの早期発見を目的にオプションで胸部CT検査を行っている施設もあります。
どんな検査?
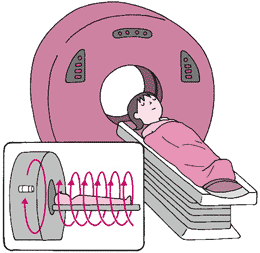
[CT(コンピュータ断層撮影)検査]
Computed Tomography(コンピュータ断層撮影)の頭文字ととってCT検査といわれています。X線を体のまわりを回転させながら照射し、そこから得られた情報をコンピュータが処理し、断層画像(体を輪切りにしたような画像)にして、体内のようすを詳しく調べる検査です。
検査は、寝台に横になったまま、ガントリーというドーム状の装置の中に入って受けます。検査時間は5分程度です。
近年はCTを改良したヘリカルCT(らせんCT)やマルチスライスCTなどが登場し、さらに診断の質が高まっています。ヘリカルCTはらせん状にX線を照射することにより連続した画像を撮影することができるので、3Dの立体的な画像が得られます。より小さな病変も発見できる特長があり、とくに肺がんの早期発見に威力を発揮しています。また従来のCTに比べ被ばく量も少なく、検査時間も短くすみます。
マルチスライスCTは、輪切りの幅を薄くしたり、複数の方向から撮影できることから、撮影時間が大幅に短縮され、従来のCT検査やヘリカルCTよりさらに鮮明な画像が得られます。
検査で何が分かる?
体のすべての部分を撮影することができるので、脳梗塞(のうこうそく)や脳出血など頭蓋内の異常や病気をはじめ、肺や肝臓、腎臓、胆のう、膵(すい)臓などなど全身のさまざまな部位の精密検査として行われています。CTだけで診断がつく場合もありますが、ふつうは超音波検査や血管造影検査などほかの画像検査と組み合わせて診断されます。
またCT検査は、骨や軟骨などの病変部の診断などでも使われます。
検査のときの注意/受けるときのポイント
X線による放射被ばくの危険があるため、妊娠している可能性のある人は検査を避けてください。また、造影剤を使う場合、過去にヨード系薬剤でショックを起こした人は、事前に申し出てください。
異常があるときに疑われる病気
脳梗塞(のうこうそく)、脳出血、くも膜下出血、動脈瘤(どうみゃくりゅう)、頭部外傷のほか、肺がん、肝がん、腎がんなどあらゆる臓器の腫瘍(しゅよう)など。
異常がみつかったら
必要に応じて、超音波検査や血管造影検査など、ほかの画像検査を組み合わせてさらに詳しい検査をしていきます。
