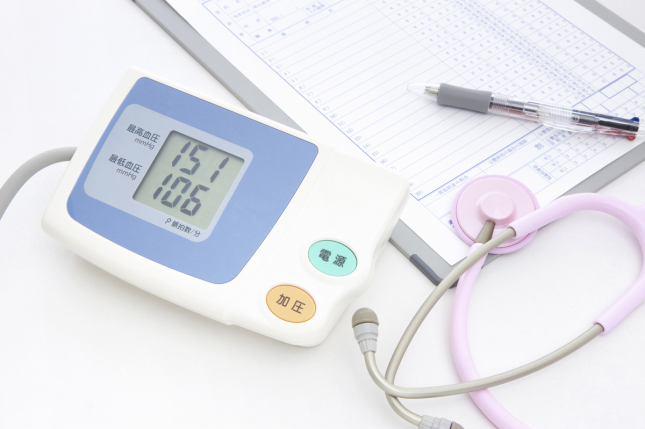
高血圧と性格には関係がある?
国民病といわれるほど身近な、そして、こわい病気の高血圧。食塩のとり過ぎや運動不足、肥満などが危険因子いわれますが、性格も高血圧と関係があるという研究結果が報告されました。どういうことでしょう?
成人の2人に1人が高血圧?
「高血圧は日本人にとって最大の生活習慣病のリスク要因」(e-ヘルスネット/厚生労働省)といわれます。
高血圧にはほとんど自覚症状がないことから、放置されやすい病気ですが、体の中では密かに動脈硬化が進行。最終的には脳卒中や狭心症、心筋梗塞、腎不全など、命にかかわる重大な病気を引き起こすといわれます。
そんなことから高血圧は別名「サイレントキラー」とか「静かなる殺人者」などと呼ばれています。
もし高血圧が完全に予防できれば年間10万人以上の人が命を失わずに済むという推計もあるそうです(e-ヘルスネット)。
「国民健康・栄養調査(令和5年)」によれば、収縮期(最高)血圧が140mmHg以上の高血圧の人の割合は、男性が27.5%、女性が22.5%でした。
20歳以上の国民の2人に1人が高血圧ともいわれています。
高血圧の最大の原因は食塩のとり過ぎ
「日本人の高血圧の最大の原因は食塩のとり過ぎ」(e-ヘルスネット)だそうです。和食は健康といったイメージの一方、しょう油やみそといった伝統的な調味料が頻繁に使われる和食は食塩が多いのが特徴ともいえます。
例えば、みそ汁、メザシやアジの干物などの焼き魚、漬け物、ソバにラーメンなどの麺類、カレーにカツ丼、肉豆腐、すき焼き、間食はせんべいに柿ピー……等々、どれも「しょっぱさ」が旨味の食べ物ばかりです。
おかげで日本人の食塩摂取量は「健康日本21(第三次)」の目標値である1日当たり7gに対して平均値で9.8g(国民健康・栄養調査/令和5年)とかなり多め。男性で10.7g、女性でも9.1gあります。日本高血圧学会の目標6g未満の約1.5倍、WHO(世界保健機関)の目標5g未満の約2倍です。
高血圧の原因は食塩の過剰摂取以外にもあって、例えば、肥満、飲酒、運動不足、ストレス、喫煙、遺伝的体質などがよく知られています。そんな高血圧のリスクとして最近、話題になったのが「性格」との関係です。
性格と高血圧リスクは関係している?
早稲田大学を中心とした国際研究グループが、日本に住む成人約7,000人を対象に4年間、新しく高血圧を発症したカテゴリーと高血圧が3年以上継続したカテゴリーに分けて追跡調査した結果、「性格が高血圧リスクを予測する重要な因子である」ことを明らかにしたといいます。
研究グループは「誠実性」「協調性」「外向性」「開放性」「神経症傾向」といったビッグファイブと呼ばれる心理学的な性格特性を用いて検証。
その結果、自己抑制的で責任感が強い傾向がある「誠実性」の高い人ほど、高血圧が新たに発症するリスクや高血圧が継続するリスクが低かったといいます。
一方、創造性や好奇心、新しい経験への興味が強い傾向がある「開放性」の高い人ほど、高血圧の継続するリスクが高かったそうです。
研究グループは、「結果の一般化の可能性は制限される」としつつ、「将来的には性格を考慮した健康支援が、高血圧をはじめ生活習慣病の予防や管理に役立つ可能性がある」としています。
性格を変えるのは難しいけど、うまく自分なりの高血圧対策を見つけられるといいですね。
野菜と果物を食べて食塩を排出?
高血圧の予防には食塩摂取量を制限することですが、とくに注意は調味料だそうです。調味料は日本人の食塩摂取源の約7割を占めるといわれ、なかでもしょう油、みそ、塩がその多くを占めています。
食塩の摂取源で若い世代に多いのは、インスタントラーメンやカレールーなど加工食品からの摂取で、高齢者は漬物からが多いそうです。
そんなことから、ラーメンなどの麺類のスープは残す、漬物はできるだけ控える、しょう油は「かけない」で「つける」などがいわれています。
食塩は「しょっぱい」ものだけでなく、いろいろな食品に使われています。ソースやドレッシング、ポン酢などの調味料はもちろん、ハムやウィンナーソーセージ、かまぼこ、さつま揚げなどの加工食品、もちろん外食やコンビニ弁当、ファストフードなどでも食塩の過剰摂取になりがちです。
減塩に加えて、果物や野菜に含まれるカリウムにはナトリウム(食塩)を排出させる効果があるそうですから、試してみてはいかがでしょう。
<参考>
*「食環境戦略イニシアチブ 食塩のとりすぎ問題」(厚生労働省)
*「さあ、減塩!」(特定非営利活動法人 日本高血圧学会)
*「性格と血圧の関係、早大チームが追跡調査」(毎日新聞/2025.8.28)
*「性格で高血圧リスクを予測」(早稲田大学 研究活動)
*「性格で高血圧リスクを予測 早稲田大学などが7300人を調査」(大学ジャーナルオンライン編集部)





