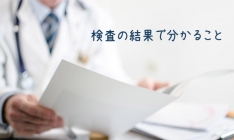「がん検診」が「がん健診」でないのは?
厚生労働省は、2016年にあらたにがんと診断された人は約100万人となり過去最多を更新したと発表しました。
がんの早期発見に欠かせないのが、がん検診ですが、よく使われる「健診」と「検診」
何が違うのでしょうか?
がん患者数、1位は男性が胃がん、女性が乳がん
日本人の2人に1人が生涯でがんにかかるといわれる時代。
厚生労働省の発表によると、2016年にがんと診断された患者数の第1位は、男性が胃がん、女性は乳がんでした。
次いで男性の場合は前立腺がん、大腸がんと続き、女性では2位が大腸がん、3位が胃がんとなっています。
働き盛りに多い女性のがん
がんの増加の背景に高齢者人口の増加が指摘されています。
しかし、それだけではありません。
食生活やライフスタイルの変化も指摘されています。
たとえば、乳がんでは30歳代から増え始め、発症年齢のピークは40歳代後半から50歳代前半だいわれています。
また、子宮頸がんは近年は20歳代~30歳代に増えていて、「ピークは30歳代後半」といわれていますから、若い世代にとっても、がんは人ごとではないのです。
「健診」と「検診」の違いって?
そして、がんの早期発見の決め手となるのが、がん検診です。
体の健康状態を調べる「けんしん」には、「健診(いわゆる健康診断、もしくは健康診査ともいいますけれど)」、それと「検診」があります。
みなさんはこの2つの違いをご存知でしょうか?
日本医師会によると、
「健康かどうか・病気の危険因子があるかどうかチェックすること」が健診で、「ある特定の病気を調べるために診察・検査を行うものが検診」です。
「検診の目的は、特定の病気を早期に発見して早期に治療することにある」としています。
そういわれてみると、検診には必ず病気の名前がついていて、がん検診もそうですが、歯科検診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検診などがありますね。
自覚症状のない人が対象
病気は、最初はこれといった症状がなく、症状があらわれた場合はすでに進行している場合が少なくありませんない。
健診も検診も自覚症状がない人を対象としています。
自分は、健康だと感じていているときに定期的に受けることがポイントだといいます。
病気の自覚症状がある人が、診断を受けることを目的に受診するものではありません。
がん検診のメリット・デメリット
がんについては、さまざまな検診がありますが、がんの部位によっては、効果があるかどうか不明であるものやがん検診を行うことで、結果的に不必要な治療や検査を招くなどデメリットもあるといわれています
しかし、メリットがデメリットを上回り、検診の有効性が科学的に証明されているものもあります。
それがすべての自治体で行っている胃がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、大腸がん検診です。
これらのがんは、特定の方法で行う検診を受けることで、死亡率が下がることが科学的に検証されているそうです。
推奨されるがん検診は、定期的に受けて自分の健康を守りたいものですね。
要精密検査といわれたら
ところで、がん検診を受診して「要精密検査」という結果が出ると、がんと診断されたような気がしてドキっとしますね。
しかし、要精密検査というのは「疑わしいところがあるので、もう少し詳しく調べてみましょう」ということ。
「要精密検査=がんの診断」ではないそうです。
「忙しいから」「がんと診断されたら怖いから」と精密検査を受けないままでいると、がんなどの病気を見つける機会を手放してしまうことになります。
怖がらずに精密検査を受けて、本当に異常がないか確認することをおすすめします。
<参考URL>
*「知っておきたいがん検診」(日本医師会)
https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/
*「がん検診の種類」(日本対がん協会)
https://www.jcancer.jp/about_cancer_and_checkup
*「がん検診について」(国立がん研究センター がん情報サービス)
https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/about_scr.html