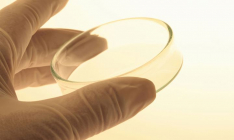どちらも「あぶら」の油と脂、何が違うの?
糖質(炭水化物)、タンパク質とともに三大栄養素の1つである脂質ですが、「あぶら」には「油」と「脂」があって混乱してしまうことも。この2つの「あぶら」、何がどう違うのでしょう?
常温では液体の「油」と固体の「脂」
脂質という「あぶら」には、ご存知のように「油」と「脂」があります。これらを油脂と呼んでいますが、常温(15〜25℃)で液体のものを「油」、固体のものを「脂」として使い分けています。
油といえばゴマやナタネ、オリーブなどの植物のタネや実を原料としている油脂のこと。脂という場合はブタやウシなどの動物の脂肪や、そこから得た油脂をさします。
ただ、魚のあぶら「魚油」は、植物油と同じように常温に置いておいてもかたまらず液体のままです。
あぶらは少量でも高エネルギー
気になるのはあぶらのエネルギーの高さとコレステロールのこと。
あぶらのエネルギー量は、油も脂も1g当たり9kcalといわれています。サラダ油でもオリーブオイルでもゴマ油でも、ブタでもウシの脂でも、あぶらはどれも1g当たり9kcalということです。
他の調味料、例えば砂糖(上白糖)は1g当たり4kcalといわれています。あぶらのエネルギー量の高さが分かります。
一方、コレステロールは動脈硬化など生活習慣病の元兇などといわれて、何かと悪者扱いを受けますが、細胞を包む細胞膜やホルモンをつくる材料として大切な栄養素だといいます。
「コレステロールゼロ」と書かれた植物油も見かけますが、植物油にはもともとコレステロールは含まれていないか、含まれてもとても微量です。
とり過ぎても、とらな過ぎても……
「あぶらは太る」というのが多くの人の認識かもしれませんが、「食べ過ぎれば太る」という点ではあぶら(脂質)も糖質やタンパク質も同類といえます。必要以上に摂取すれば余分なエネルギーとして体に蓄積されます。
逆にあぶらを食べるのを制限したり控えると、ホルモンバランスの乱れ、免疫機能の低下や肌荒れなどを招きます。
脂質は糖質(炭水化物)、タンパク質とともに体に必要な栄養素です。厚生労働省は1日の脂質の摂取目標量を全体の20〜30%(うち動物の脂に含まれる飽和脂肪酸については7%以下)としています。
動物の脂より魚の油を食べたい?
「魚の油は頭をよくするし、体にいいからたくさん魚を食べよう」といったことをよく耳にしますよね。
魚の油は不飽和脂肪酸といって植物の油と同じ脂肪酸に分類されます。EPA(エイコサペンタエン酸)とかDHA(ドコサヘキサエン酸)といったおなじみの脂肪酸は魚の油に多く含まれています。血液をサラサラにする、LDL(悪玉)コレステロールを減らしてHDL(善玉)コレステロールを増やすなど、さまざまなうれしい効果が期待されています。
逆に動物性の脂には飽和脂肪酸が多く含まれ、食べ過ぎるとLDLコレステロールや中性脂肪を増やし心疾患の発症リスクを高めるといわれます。
「見えないあぶら」と「見えるあぶら」
「あぶら(油脂)」には「見えるあぶら」と「見えないあぶら」があります。
植物油やバター、マーガリン、マヨネーズなどは「見えるあぶら」ですが、肉類や卵、牛乳、魚介類、お菓子類、調味料類、パン類などには、食品自体に油脂が含まれていて、あぶらが「見えない」状態です。
1日に摂取される脂質のうち、植物油など「見えるあぶら」からの割合は約2割で、残りの約8割は肉類やお菓子など「見えないあぶら」から摂取されているといいます(厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」)。
ところで動物性の脂には脳の「報酬系」の神経が刺激され、強い依存性があるといわれ、その威力は「麻薬をも凌ぐ」らしいです。
脂系っておいしいですよね、ホントに。
<参考>
*「油に関するQ &A」(日清オイリオグループ株式会社)
*「三大栄養素の一つ!脂質について知って欲しいこと:動物油脂」(九州大学附属図書館ウェブサイト)
*「健康に役立つ魚の油」(一般社団法人 全国海水養魚協会)
*「特集 脱メタボ大作戦(栄養と料理2023年10月号)」(女子栄養大学出版部)