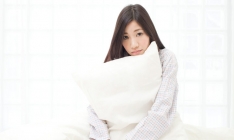コロナ禍と不眠
「睡眠で休養が取れていない」「不眠がある」など、日本人の5人に1人は睡眠の悩みを持っているといわれています。
コロナ禍で生活リズムが乱れて、よい睡眠がとれないという声も多く聞きます。
今回は改めて不眠について考えてみます。
コロナ過で増える不眠の悩み
コロナ禍における睡眠、みなさんはいかがですか? ぐっすり眠れていますか?
クラシエ薬品株式会社が、全国の20代~60代の男女200人を対象に行った不眠の実態調査によると、新型コロナウイルス感染拡大以降、約4割の人が「不眠の症状を感じたことがある」と回答したそうです。
多い悩みは「中途覚醒」
年代別でみるともっとも多かったのが50~54歳で全体の約6割を占めており、次いで多かったのが45~49歳でした。
不眠の症状については、もっとも多い回答が「途中で目が覚める(72.4%)」でした。2位は「寝つきが悪い(53.9%)、3位は「熟睡感がない(38.2%)」と続きます。
中途覚醒というのは、眠りが浅くて寝ている間に目が覚めてしまうこと。
中途覚醒があると、寝床についている時間が長かったとしても、熟睡したという満足感が得られません。
「中途覚醒」で考えられる原因
不眠の原因はさまざまですが、中途覚醒の場合、原因のひとつに「体内時計」の乱れがあるといわれています。
コロナ禍では、リモートワークなどで生活のリズムがつけにくく、日中の活動量も減る傾向にあります。
加えて、オフィス通勤がなくなることで朝、日光を浴びる量も減りがちです。
私たちの体は、朝、光を浴びてからおよそ14時間後に睡眠を促進するホルモン「メラトニン」の分泌が始まるそうです。このメラトニンの分泌が減るために、中途覚醒しやすいと考える専門家もいます。
また、寝つきの悪い入眠障害も含めて、不眠にはストレスも大きく関わっていることが知られています。
心身の疲れがとれない
眠りは心身の疲労を回復させます。
このためよい睡眠がとれていないと、疲労が解消されないばかりでなく、最近では肥満や高血圧など生活習慣病のリスクが高まることもわかってきたそうです。
また、睡眠による休息感が低い人ほど、気分が落ち込んだり憂うつになったりする「抑うつ」の度合いが高くなるという研究結果もあるそうです。
心と体の健康を保つためには、快眠こそが大事なキーポイントになるようです。
よい眠りに導くために必要なこと
厚生労働省の「健康づくりのために睡眠指針」では、よい睡眠をとるためには適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリをつけることをすすめています。
眠りを司る体内時計は、起床直後に朝起きて日光を浴びることで自然とリセットされます。体内時計のリセットができないと、寝付くことのできる時間も少しずつ遅れてしまうそうなのです。
つまり、眠くなる時間は、朝起きて太陽の光を浴びることで決まってしまうというわけです。
準備を整えて、眠りやすく
また体内時計の機能を高めるためには、糖質とたんぱく質を含んだバランスの良い朝食をしっかりとることだといいます。
ほかにも夕方からはお茶やコーヒーなどのカフェイン入りの飲み物は避ける、就寝の2~3時間前にぬるめのお風呂にゆっくり入る、また白っぽい昼白色の蛍光灯は体内時計を遅らせる作用があるため、夜は赤っぽい暖色系の蛍光灯にするなど、眠りに入る準備を整えることも必要だといわれています。
睡眠中はアンチエイジングを助ける成長ホルモンがたくさん分泌されるそうですから、美容のためにもよい睡眠をとりたいものですね。
「ぐっすり眠れない」とあきらめてしまわずに、まずは積極的に生活リズムを整えてみませんか?
<参考>
*クラシエニュースリリース「コロナ禍で不眠が増加!? 不眠に関する調査と漢方」(クラシエ薬品株式会社)
*「健康づくりのための睡眠指針2014」厚生労働省)
*「不眠の悩み」(MHK出版『きょうの健康』2021年3月号)
*「ポジティブ睡眠でいこう!」(女子栄養大学出版部『栄養と料理』2019年8月号)
*e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」(厚生労働省)