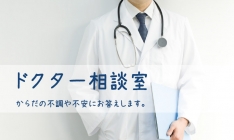若い世代の難聴リスクにご用心!
イヤホンを装着して、スマートフォンで音楽やゲーム、動画を楽しんでいる人も多いはず。
中にはイヤホンをしたまま寝てしまうという人も。
でも使い方に注意しないと「ヘッドホン・イヤホン難聴」の危険があります。
WHOの警告
スマートフォンの普及と通信速度の向上で、場所を問わずに音楽や動画を楽しめるようになりました。
その反面「ヘッドホン・イヤホン難聴」といわれるトラブルが、世界的に問題になっているようです。
2015年、WHO(世界保健機関)は、世界の12~35歳の若者の約50%がスマートフォンやポータブルオーディオ機器の使用で、約40%がナイトクラブやイベントなどで許容範囲を超える大きな音を聞いていると警告。
世界中の11億人ほどに、将来難聴になる危険性があると発表しています。
なぜ難聴が起こるのか
大音響で聞くことと難聴は、どのような関係があるのでしょうか?
そもそも音の伝達経路は、外耳道→鼓膜→蝸牛へと伝えられて、蝸牛から聴神経へ信号が送られることによって、音が感知されるといわれています。
この伝達経路の中で、蝸牛で音を伝える役割をしているのが蝸牛の内部にある「有毛細胞」と呼ばれるものなのだそうです。
大音量で音楽などを聞き続けていると有毛細胞が徐々に破壊されて、ヘッドホン・イヤホン難聴が起こるといわれています。
有毛細胞が壊れる前であれば、耳の安静を図ることで回復するそうなのです。しかし、有毛細胞が一度壊れてしまうと、残念ながらもう元には戻せないといいます。
自覚症状がないまま進行する
この難聴の怖いところは、自覚がないまま症状が徐々に進行することが多いということ。
ヘッドホン・イヤホン難聴は、はじめは高い音域から聞こえにくくなるといいます。けれども、ふだん私たちが会話している声の高さはそれよりも低いために、高音が聞こえにくくなっても不便を感じないので、耳の聞こえが悪いことに気づかないことがあるそうです。
専門家は、耳の塞がった感じや耳鳴りがする、また聞こえ方がおかしいと感じたときは、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診するようにすすめています。
耳に優しい生活を心がけよう
では、どうしたら防げるのでしょう?
WHOとITU(国際電気通信連合)が進めてきたSafe Listening標準化に基づく安全利用の目安は、「1週間の安全な音の目安は、地下鉄の車内に相当する音量80デシベル(子どもは75デシベル)、1週間に40時間まで」としています。
難聴を予防するためには「イヤホンを使って音を聞くのは1日1時間未満にする」「イヤホンで聞く場合は最大音量の60%以下にする」ことが大事だといわれています。
また、鉄道など騒がしい場所で聞く場合にはノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使えば音量を上げずにすみます。音量を大きく上げなくても聞こえやすい骨伝導タイプなどのイヤホンを選ぶことも、1つの方法だそうです。
大事な耳をいたわる、ちょっとした心がけが必要のようです。
<参考>
*「ヘッドホン難聴」(千葉医師会 リーフレット)
*e-ヘルスネット「ヘッドホン難聴について」「有毛細胞」(厚生労働省)
*「快聴で人生を楽しく」(日本耳鼻咽喉科学会)