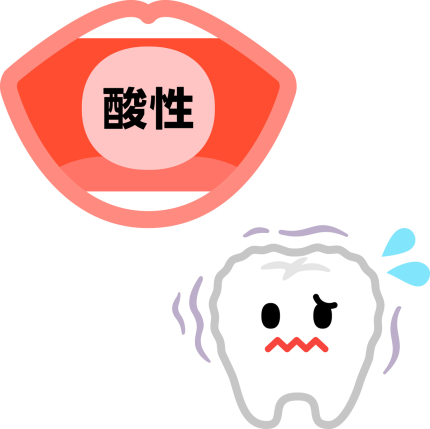
炭酸飲料で歯が溶ける「酸蝕症」とは?
ふだん何気なく飲んでいる炭酸飲料や乳酸菌飲料などの清涼飲料水、ワインや酎ハイなどのアルコール飲料のなかには、それと気づかないうちに歯を溶かしてしまうものがあるとか。
どういうことでしょう?
「酸蝕症」は第3の歯の疾患?
歯が酸に弱いことはよく知られています。
歯の疾患ではおなじみの虫歯も、ミュータンス菌に代表される虫歯菌が歯の表面にはりついて酸をつくり歯を溶かしていくといわれます。
歯の表面をおおっているエナメル質はとても硬い組織なのですが、強い酸にふれると簡単に溶けてしまい、その下にある象牙質がむき出しになり、虫歯がどんどん進行するといいます。
一方、歯が酸によって溶けてしまうことを「酸蝕(さんしょく)」といい、毎日の食生活でも酸性の食べ物や飲み物に歯がさらされることで起こるといわれます。
こうした長い時間をかけて酸が歯を溶かしてしまう「酸蝕症」もしくは「酸蝕歯」と呼ばれる現象が最近、増えているといいます。
虫歯、歯周病に続く第3の歯の疾患として注目されているようです。
4人に1人が「酸蝕症」の疑い?
酸蝕症は虫歯と違って虫歯菌のような細菌がつくる酸ではなく、酸性の飲食物などで、歯が「化学的」に溶けてしまう状態のことを指します。
「酸が歯を蝕む」というこの酸蝕症。日本人の約4人に1人がかかっているといわれています。
酸蝕症にかかると、「冷たいものや酸っぱいものが歯にしみる知覚過敏」「歯の凸凹がなくなり全体が丸みを帯びる」「前歯が薄くなり象牙質が透けて見えたり、欠けたり、ヒビが入ったりする」「歯の詰め物が浮き上がる」などの症状が見られるといいます。
炭酸飲料や酢飲料、ワインなどに注意
酸蝕症の原因といわれるものの中で注意したいのが、酸性度の高い飲み物や食べ物などを習慣的に摂取することといわれます。
例えば柑橘系の果汁が入ったジュースや乳酸菌飲料、炭酸飲料やスポーツ飲料はもちろん、黒酢などの酢飲料や栄養ドリンクなど、健康をうたう飲食物の中には高い確率で酸が含まれていると専門家は指摘しています。
これらを継続して摂取することによる酸蝕症のリスクは数倍から数十倍にもなるともいわれています。
健康に配慮して飲んだり食べたりしているつもりが、逆に「健康を害しているかも」とは悩ましい限りです。
また、ワインやビール、酎ハイなどのアルコール類、酢の物、梅干し、ポン酢やマヨネーズなども、「適度な摂取を」といわれています。
飲食物以外の要因には、胃食道逆流症や摂食障害、アルコール依存症などの内因的要因も酸蝕症のリスクとして指摘されています。
酸蝕症を防ぐために「どうする」?
口の中はふだん唾液の中和作用によって中性(pH7前後)に保たれています。
pHは数値が低いほど酸性度が高く、レモンはpH2.1です。
他にも商品によってpH値は違いますが、乳酸菌飲料はpH3.6、スポーツドリンクはpH3.5、赤ワインはpH3.4です。
歯のエナメル質が溶けはじめるのはpH5.5といわれます。ちなみに胃液はpH1.0~1.5、胃の中はpH2.0だそうです。
酸蝕症を防ぐにはどうすればいいのでしょうか?
健康のことを考えると酸性度が気になる食品をまったく飲食しないわけにはいきません。うまく付き合う方法はあるでしょうか?
飲食後、30分は歯みがきは避ける?
「飲み食べ後は、水やお茶で口をゆすぐ」「間食や食事のダラダラ食べ、ダラダラ飲みはしない」「寝る前の飲食は控える」とよくいわれます。
また、食事のときは「よくかむ」のがいいようです。
かむことで唾液が多く分泌され、酸性に傾いた口の中を中性に戻したり、唾液による歯の再石灰化(修復)が促されるといいます。
食後の歯みがきにも注意が必要のようです。
酸性の飲食物を摂ったあとはすぐに歯みがきをしないことが肝心とか。お茶や水を飲んだり口をゆすいだりして、最低でも30分は歯みがきを控えるのが酸蝕の予防には効果的だそうです。
「歯は健康の入り口」といいます。大切に付き合って行きましょう。
<参考>
*「食品やサプリメントで歯が溶ける?酸蝕症をご存じですか?」(国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所)
*「農家の健康便利帳」(発行・万来舎/発売・エイブル)
*「歯が溶ける!?『酸蝕症』とは?」(公益社団法人神奈川県歯科医師会)

